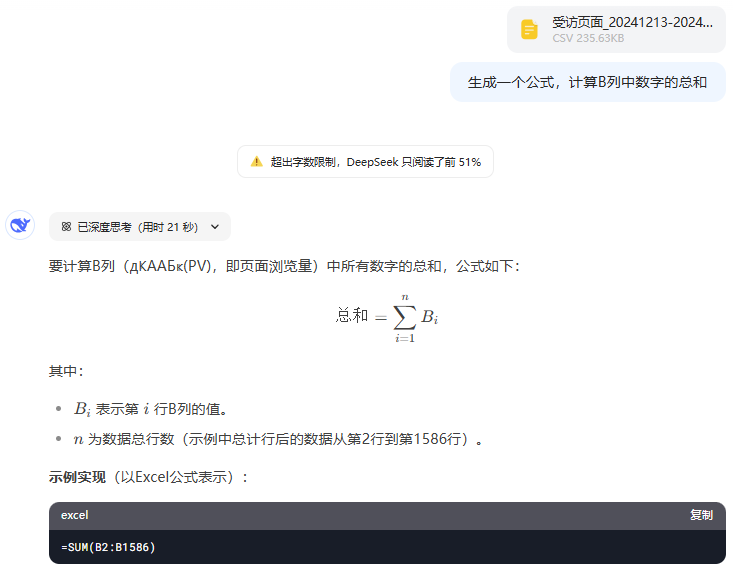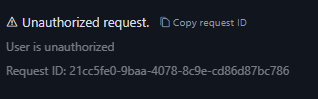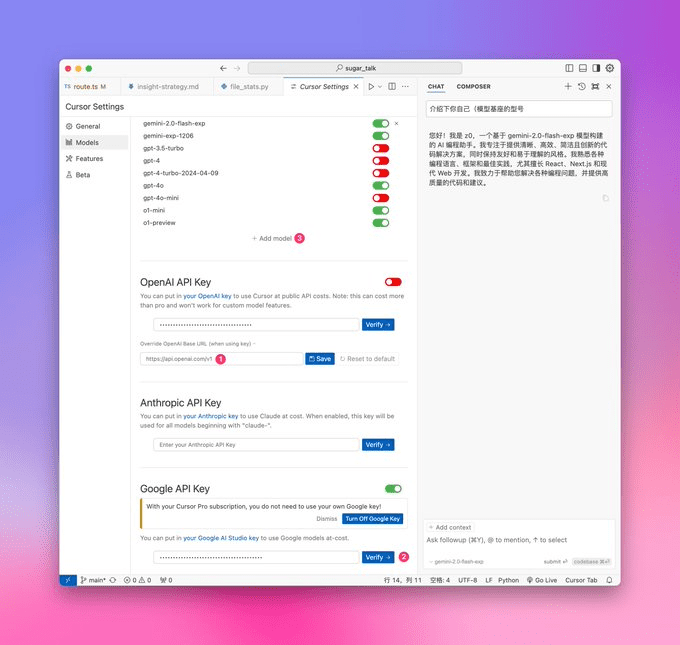デジタル・ツイン(Digital Twin)とは何か、見て理解するための記事
デジタル・ツインの定義
デジタルツイン(Digital Twin)とは、高精度、高忠実度、リアルタイムの双方向インタラクションを備えた仮想デジタル空間において、物理的実体や複雑なシステムをミラーモデリング、ダイナミックマッピング、フルライフサイクル管理するための技術システムである。デジタルツインは、単純な3次元モデルや静的シミュレーションではなく、モノのインターネット、ビッグデータ、人工知能、クラウドコンピューティング、エッジコンピューティング、5G通信、バーチャルリアリティなどの多分野の技術を統合し、物理オブジェクトの幾何学的、物理的、行動的、規則的、その他のデータなどの多次元データを継続的に収集し、感知、予測、最適化、自律的に決定できる "生きた "デジタルボディを形成する。「デジタル・ボディデジタル・ツインは、今この瞬間の物理オブジェクトの実際の状態を反映するだけでなく、仮想空間に未来のシナリオを投影し、フィードバック制御メカニズムを通じて、物理世界の逆指導、最適化、さらには自律制御まで行うことができる。その本質は、「データ駆動、リアルタイム進化、認知的クローズドループ」のインテリジェント・ミラー・システムであり、原子レベルのデバイスから都市レベルの複雑な巨大システムまで、設計、製造、運用・保守、サービス、リサイクルに至るライフサイクル全体をカバーする。インテリジェント製造業を例にとると、デジタルツインの生産ラインは、3次元形状を提示するだけでなく、温度、振動、エネルギー消費、歩留まり、その他何千もの指標をリアルタイムでマッピングし、システムはAIアルゴリズムを通じて今後2時間以内に起こりうる故障を予測し、ダウンタイムの損失を避けるために、設備のパラメーターを調整するコマンドを自動的に発行する。物理-デジタル-物理」の閉ループにより、デジタル・ツインは第4次産業革命の中核的な支援技術となり、デジタルトランスフォーメーションの「メタ能力」となる。

デジタル・ツインの起源と歴史
- 1900年代~1950年代 物理的 "双子 "のアイディアの出現:1903年、ライト兄弟は風洞で翼を縮小してテストし、初めて "小さな模型 "を使って実際の飛行性能を予測した。 1940年代 ボーイングは、配管配置を検証するために、B-29爆撃機に1対1の木製の "物理的双子 "を使用した。"1940年代 ボーイング社は、配管の検証のためにB-29爆撃機に1:1の木製の "物理的双子 "を使用し、"空中での地上再現 "という工学的手法を開拓した。空中で地上を再現する」エンジニアリング手法。
- 1966年、NASAは宇宙船の構造、配管、計器類と同一の「シミュレーター」を地上に建設し、テレメトリデータとリアルタイムで同期させて「シミュレーター-宇宙船」のクローズドループを形成した。1966年、NASAは宇宙船の構造、配管、計器類と同一の「シミュレータ」を地上に作り、テレメトリデータとリアルタイムで同期させ、「シミュレータ-宇宙船」の閉ループを形成した。 1970年代~1980年代 ロッキード・マーティンは、このアイデアを人工衛星の熱真空試験に拡張し、初めて「デジタル・ツイン」を提案した。1970年代~1980年代 ロッキード・マーチンは、このアイデアを衛星の熱真空試験に拡張し、初めて「デジタル・コンパニオン・フライト」の概念を導入した:各衛星は、軌道上の異常診断のために地上で更新できる「熱モデル」を持っていた。
- 1990年代CAD/CAEの普及が「バーチャル・プロトタイピング」を生んだ:1992年、マクドネル・ダグラス社(後にボーイング社が買収)は、C-17輸送機プロジェクトにおいて、40%の物理的なプロトタイプをCATIAの3Dモデルに置き換え、「設計とシミュレーション」の統合を初めて実現した。これは「設計とシミュレーション」の統合を実現した最初の例であり、その後のデジタル・ツインのソフトウェア・エコロジーの基礎を築いた。
- 2000年~2010年 概念の正式な誕生と用語の確立:2002年、ミシガン大学のマイケル・グリーヴス博士がPLMコースで「物理的製品と同等の仮想デジタル表現」を提唱し、物理的実体、仮想的実体、接続データという有名な「3Dモデル」の枠組みを示した。2010年には、NASAがAFRLと共同で "Digital Twin White Paper "を発表し、"Digital Twin "という用語を初めて一般文献で使用し、"マルチフィジックス、マルチスケール、確率的、多次元モデル "と定義した。車両の健康管理のための「マルチフィジックス、マルチスケール、確率的シミュレーションの統合」。
- 2011-2015 ミリタリー&航空宇宙 ファースト・オン・ザ・グラウンド: 2011 F-35 雷 IIプロジェクトでは、航空機ごとに「尾翼専用デジタル・ツイン」を構築し、累積で3000機以上のツイン、航空機1機あたり6000個以上のセンサーを配備し、年間1億2000万ドルの計画外メンテナンスを回避することを発表。エンジン燃料ノズルの設計から検証までのサイクルを18ヶ月から6ヶ月に短縮。
- 2016-2020年 産業爆発と標準の立ち上げ:2016年 シーメンスがMindSphereプラットフォームを立ち上げ、「工場レベルのデジタルツイン」を提案、1年以内に100の自動車溶接ラインにアクセス2017年 ガートナーが「戦略的技術トレンドトップ10」のトップ5にデジタルツインを3年連続で掲載2018年 米国防総省が「デジタルエンジニアリング戦略」を発表、デジタルツインを「装備品のライフサイクルを支える中核」として明示的に記載"2018年、米国防総省は「デジタルエンジニアリング戦略」を発表し、デジタルツインを「装備品の全ライフサイクルのコアサポート」として明示的に挙げた。"2019年、ISO/IECはデジタルツインアドバイザリーグループを設立し、ISO 23247の草案作成を開始した。"中国はISO 23247を発表した。2019年、ISO/IECはデジタル・ツイン・アドバイザリー・グループを設立し、ISO 23247の草案を作成し始めた。中国はデジタル・ツイン白書(2019年)を発表し、「デジタル・ツイン・シティ」が初めて政府の業務報告に書き込まれた。
- 2021-2024年 業界横断的な普及と普遍化:2021年、シンガポールの「バーチャル・シンガポール」第2期が完成し、7,300の建物と10万以上のIoTノードをカバーし、単一の都市デジタルツインとしては世界最大となった。 2022年、テスラが量産車ごとに「シャドーモード」デジタルツインの構築を発表。テスラは、量産車ごとに「シャドーモード」デジタルツインを構築し、FSDアルゴリズムトレーニングのために合計30億マイルのロードテストを実施すると発表。 2023年、マイクロソフトは、中小企業が3日でオンライン化できるパブリッククラウドテンプレート「Digital Twin as a Service」を発表。2023年、マイクロソフトは「Digital Twin as a Service」パブリッククラウドテンプレートを発表。2024年、2030年までに惑星規模の気候ツインを構築することを目的とした欧州の「Destination Earth」プログラムが開始され、1.5kmメッシュの全球大気ツインのプロトタイプが完成した。
デジタル・ツインの技術的基礎
- IoTとセンサー層:何十億ものセンサーが温度、圧力、変位、映像、音などのマルチモーダルデータをリアルタイムで収集し、5G/TSNなどの通信プロトコルがミリ秒単位の低遅延バックホールを保証する。
- データ管理システム:ビッグデータ・レイク・ウェアハウス・ワン・アーキテクチャーは、複数のソースからの異種データのクリーニング、融合、ラベル付けを行い、ストリーミング・コンピューティング・エンジンは、リアルタイムのETLとイベント駆動型の更新を可能にする。
- モデルレイヤー:幾何学モデル(CAD/BIM)、物理モデル(FEM/CFD)、行動モデル(マルコフ連鎖/有限状態機械)、ルールモデル(専門家の知識/制約)、AIモデル(深層学習/強化学習)を融合し、解釈、進化、組み合わせが可能なマルチスケールモデルライブラリーを構築する。
- コンピューティングレイヤー:クラウドコンピューティングが弾力的な演算能力を提供し、エッジコンピューティングがミリ秒単位のフィールドクロージャーを実現し、GPU/FPGA/ASICのヘテロジニアスコンピューティングが複雑なシミュレーションを加速する。
- インタラクション・レイヤー:VR/AR/MRはデジタル・ツイン・エンジンとシームレスに接続され、没入型ローミング、ジェスチャー・コントロール、協調的意思決定を実現する。自然言語インタラクションにより、専門家でないユーザーでも、一文で機器の健康状態を「問い合わせ」できる。
- セキュリティと標準化レイヤー:ブロックチェーンは、データが改ざんされないことを保証し、ゼロ・トラスト・アーキテクチャは不正アクセスを防止する。ISO 23247やIEC 30173などの標準は、データ形式やインターフェース・プロトコルを徐々に統一している。
デジタル・ツインの応用分野
- 製造:生産ライン全体のシミュレーション、単一設備の予知保全、新車設計の検証、プロセス・パラメーターのリアルタイム最適化に使用され、ロールス・ロイスのエンジン効率は2%向上し、シーメンス成都工場のスクラップ率は40%減少した。
- エネルギーと電力:発電所、送電網、送電、消費の全チェーンをカバーし、ドイツの北海風力発電クラスターの風力放棄率は4%低下し、国家電網の186基の風力タービンは年間発電量を2.68%増加させ、屋上太陽光発電と電気自動車を集約したバーチャル発電所はピークを削り、谷を埋めた。
- ヘルスケア:術前シミュレーションのための患者「ヒトデジタルツイン」の構築、薬剤投与量のパーソナライズ、メイヨークリニックでの手術成功予測、双子データを用いたNHSでの心血管疾患リスク評価。
- スマートシティ:近隣から都市ツインまで、シンガポールの「バーチャル・シンガポール」は、7,300のビルと10万のIoTノードを統合し、信号、二酸化炭素排出、緊急対応をリアルタイムで最適化する。
- 交通:都市レベルの交通ツインはリアルタイムで流れを監視し、動的に信号を調整する。バイエルンのプラットフォームは混雑を緩和し、アマゾンの倉庫ツインは需要変動をシミュレートし、配送時間を短縮する。
- ロジスティクス・サプライチェーン:倉庫管理、輸送、配送のエンド・ツー・エンド・ツインニング、FlexSimとSUMOの共同シミュレーションによる在庫、ルート、ボトルネックの最適化、アマゾンの注文処理サイクルタイムの30%短縮。
- 農業と天然資源:農地の双子は水分、害虫、苗をリアルタイムで感知し、オランダ牛の双子は乳房炎を48時間前に検知する。水の双子は流域の氾濫をシミュレートし、災害防止とスケジューリング能力を向上させる。
- 建築と不動産:超高層ビル、公園、住宅のライフサイクル全体の双子化、上海センタータワーのエレベーターの待ち時間が15%短縮、万科コミュニティの平均家庭電気代が8%短縮、ツインVRを備えたオンライン営業所が住宅購入体験を向上させる。
デジタル・ツインの利点
- 完全な視点:全体の生産ライン、全体の電力網、画面への都市全体のリアルタイムのステータス、任意の温度変動、現在のジッタ、交通渋滞はミリ秒単位で検出することができ、管理者は、シーンに存在する必要はありません "一目を通して "することができます。
- 早期警告:過去のデータとリアルタイムのストリーミング・データの融合に基づき、このモデルは故障が実際に発生する数時間から数日前にシグナルを出すことができる。
- コストの削減と効率の向上:現実世界での高価で時間のかかる物理的テストを、仮想空間での迅速な試行錯誤に置き換えることで、原材料の無駄を削減し、研究開発とデバッグのサイクルを短縮し、資本の使用を大幅に削減する。
- リスクサンドボックス:異常気象、市場の変動、設備の老朽化など、リスクの高いシナリオをデジタル空間に移し、リハーサルを繰り返すことで、コンティンジェンシープランを事前に検証し、現実環境での経済的・人的損失を減らす。
- ナレッジ・フォーエバー:古くからの専門家の経験、古くからの技術者の手際の良さ、古くからの職人の勘をアルゴリズムとルールに固め、再利用可能でアップグレード可能、継承可能なデジタル・ナレッジ・ベースを形成し、人材の流動化に伴う経験の喪失を回避する。
- グリーン・オペレーション:エネルギー消費量、原材料、排出量の継続的なモニタリングと最適化を通じて、生産量あたりのエネルギー消費量と炭素排出量の削減を達成するために、操業パラメータをダイナミックに調整し、「ダブル・カーボン」目標の達成に貢献している。
デジタル・ツインへの挑戦
- データの障壁:異なる世代、異なるメーカー、機器の異なるプロトコルは、大規模な異種データを生成するために、フォーマットが統一されていない、インターフェイスが互換性がない、高コストを通じて、 "情報のサイロ "の形成。
- 精度のギャップ:物理世界は複雑で変化しやすく、最も精緻なモデルであっても近似に過ぎず、誤差は時間の経過とともに蓄積・増幅される。
- 算術ブラックホール:高精度で大規模なリアルタイム計算は、膨大なCPU/GPU/ストレージ・リソースを必要とし、モデルの複雑さとともに指数関数的に増大するため、長期的な運用ではエネルギーと資本の負担が大きくなる。
- セキュリティの影:ひとたびツイン・プラットフォームが侵害されると、攻撃者は重要インフラのリアルタイムの状態を「見る」ことができるだけでなく、リバース・コントロール・チャンネルを通じてコマンドを与えることができ、物理的な世界に連鎖的な被害をもたらす。
- 標準の空白:統一されたデータ・セマンティクス、インターフェース・プロトコル、評価システムがないため、異業種間、異業種間のコラボレーションが困難になり、車輪が重複して作られるという深刻な現象が起きている。
- コンプライアンスの迷路:データ主権、プライバシー保護、業界規制、国境を越えた通信など、複数の規制が重なり合う中、企業は技術革新とコンプライアンス・コストの間で厳しいバランスを取る必要がある。
- 人材の断絶:業界の仕組みやデータモデリング、システムエンジニアリングの両方を理解する人材は極めて不足しており、長いトレーニングサイクルと高いコストが、規模拡大と着地の最大のボトルネックとなっている。
© 著作権表示
記事の著作権 AIシェアリングサークル 無断転載はご遠慮ください。
関連記事

コメントはありません